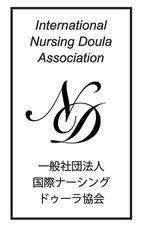ナーシングドゥーラ誕生秘話
産後や育児中のお母さんの暮らしをご家族と協力しながらお手伝いする看護職「ナーシングドゥーラ」。
その養成は2016年8月設立した「一般社団法人国際ナーシングドゥーラ協会」で開始しました。
その誕生は代表理事である私の個人的な経験からスタートしています。
その経緯をお伝えすると共に、多くの人に「ナーシングドゥーラ」というナースも産後退院後のお母さんも家族も笑顔になれる働き方を知っていただきたいと思います。
共働きと愛犬の死
私は昭和30年代生まれ。
小さい頃はたくさんの親戚と愛犬との賑やかな日々でした。
しかし、男女平等という時代の流れの先端を行っていた母親は、私が小学一年になると同時に早朝から夜まで働くようになりました。
そして、小六から大好きな父は単身赴任に。
その冬には愛犬の死。
それがきっかけか「家族」について関心を持つようになりました。
また、高校時代の友人が父親の在宅療養を手伝っているため大学進学を諦めたという話しを聞き、訪問看護という仕事に興味を持ちました。

全人的ケアを学びたい。看護大へ入学。
兄姉が母の期待を背負って有名大学に進学する中、私は学歴に全く興味が無く、人の役に立つ仕事につきたい、特に訪問看護に関心を持ちました。
そんな時「看護師は「師」。
人間として、全人的に、成長することが大切という日野原重明先生の言葉に惹かれ、聖路加国際看護大学に入りました。

ドゥーラとの出会い
入学後、終末期や高齢者ばかりだと思っていた訪問看護でしたが、大学卒業時に小林登先生の「ドゥーラ」に関する論文(1984 周産期医学)に出会いました。
「こどもの笑顔には家族が大切」
という先生の考え方に共感しました。

医療スタッフとしての経験
そこで、訪問看護の先駆者である聖路加国際病院の公衆衛生看護部に入職しました。
医師とカルテを共有した「看護」が行われていて、もともと理系の私にとってはとても学びが多い日々でした。
また、新生児訪問や乳児健診、予防接種、産婦人科外来や女性ドック等を担当して「理論に基づいた保健指導」を学びました。
その際、先輩の保健指導が素晴らしく、私はどうなんだろうという素朴な疑問から面接や指導をテープに録音させていだたき、相手がどういう風に感じるのかを勉強しては、自らの保健指導に生かしました。
これは受け手目線の看護を提供することを大事にしている自分としては、とても役に立ちました。
さらに院内研究で行った「外来の待ち時間を短縮するための実証実験」を通してシステム作りの楽しさを知りました。

緊急手術、不妊宣告、激症妊娠悪阻で離職。
焦る日々。

同級生がどんどん院内看護師としてキャリアを積む中、ともかく焦る日々。
とはいえ、深川という人情あふれる町で、周りの人からの品ある優しさに助けられながら、試行錯誤の育児。
いつか、この経験を活かす日が来る、
いや、活かしてみせるという気持ちで7年が過ぎました。
スウェーデンでの子育て
長女が一年生になった頃、
夫がスウェーデンに留学することになりました。
友人や先輩、親戚からは「旦那さんだけ単身で行かせればいいじゃないか。」と言われましたが、
しかし、私自身が父親の単身赴任でとても寂しい思いをしたのと、
「子育て支援」が充実していると言われていた北欧の暮らしに興味があり、生後3ヶ月だった第3子含めて家族五人で渡欧しました。
当時スウェーデンでは、女性は出産翌日に退院しました。
母子の心身の健康を、地域の看護師が通い、産休中のパートナーと共に守る仕組み「コミュニティナース」がありました。
退院指導でたくさんの情報を提供する当時の日本のシステムとは異なり、退院後の頻回な訪問で、沐浴や授乳・室内整備や父母の食事まで、家族の暮らし作りをお手伝いする看護師の仕事があることを知りました。
子育てのスタート期にパートナーやいろんな人の手を巻き込める仕組みがあると子育てもが楽しくなる。
私の子育て期もそういえば、下町にはそういう人がたくさんいたなと思い出してきたのです。
あの人、この人、そのご家族が居たからなんとかやれた。

産後の援助者選定要因研究
帰国後、日本はどうなっているのだろうという疑問から大学院に進学し、早速、
「産後退院後の支援者選択要因」ついて研究しました。
産科病棟入院中の約100人の褥婦さんへの聞き取りとアンケート調査結果から
「産後の支援者として不適切と判断」、
つまり
「家事や育児ができない人的資源」と知りつつ、
夫や実母を産後支援者として「仕方なく」「他にいないから」と選択している事が予測されました。
日本の女性が置かれている厳しい状況を知り、産後に適した支援者を選べるよう、夫や祖父母への教育含めた支援者育成をしたいと考えはじめました。

ドゥーラデビュー
その頃、東京都助産師会主催で「産後ドゥーラ」を育成するという話を江東区助産師会から聞き一期生として学びはじめました。
しかし「看護師」を「上から目線」と批判する同期や講師に会い受講期間は大変つらい経験でした。
ところが、認定後すぐにうつ病の方からサポート依頼があり看護師資格をもつ産後ドゥーラ、としての仕事が始まったのです。
その後、口コミであっという間に忙しくなり勇気づけられました。
もちろん、家族支えるのはひとりでは難しいと、チームサポートをしようとしましたが、協会から個人事業主同士の情報共有を禁止されていたので、チームカンファレンスする事すら出来ません。
また、健康に関する価値観のズレ(予防接種反対・医師や看護職への批判・民間療法推進等)があり他の産後ドゥーラと共に働く事に抵抗がありました。
さらに、メンタルケースを一人で抱え「鬱」になってしまった同期の非看護職産後ドゥーラを見て、、、
看護職ドゥーラの必要性を感じました。
看護的な視点で責任ある産後支援を提供するために。
病院と地域との間で孤立する家族を減らすために。
医療機関と連携した産後支援を行うために。
看護職ドゥーラの必要性を感じたのです。

ナーシングドゥーラ協会設立
そんな産後支援者とどのようにしたら出会えるか、育成しようかと悩んでいた時に、たまたま以前職場で一緒に働いていた聖路加国際病院の草川医師と再会しました。
NICUのセンター長である草川医師としても、昨今のNICU卒児の増加や異常出産の増加を鑑み、医療情報を共有できるナースが産後支援者としていたら
医師も安心して患者さんをお願いできるという話を伺い草川医師の協力を得て「ナーシングドゥーラ®」と命名し協会を立ち上げ育成をしはじめました。
医療保険や介護保険等の訪問看護ではできない育児・家事・他の家族の看病・シッティングはもちろん、Wケアをされているお母さんのお手伝いができる看護師「ナーシングドゥーラ®」は、まさに私がスウェーデンで出会ったスーパー地域ナースです。
子育て中の家族の生活に寄り添い生活の中で出てくる悩みに寄り添いつつOJTで保健指導ができる。
そして、お母さんとともに地域に出かけて、周囲の人を巻き込んでるネットワークを作ってフェードアウトする。
こんな楽しい看護はありません。
全て未熟なこどもとご両親と一緒に、試行錯誤しながらも、そのこどもがスクスクと育つ過程を支えられるのは私がめざした「子育てを支えともに楽しむ寄り添い人」です。
こんな楽しい看護を多くの方に経験していただきたいです。

潜在看護師とママを笑顔に。
厚労省の調査によれば、育児や介護や結婚等で現在就業していない看護師は71万人。
その80%が自分の育児家事と看護との両立が勤務時間が合わないという理由で復職を断念しています。また、日本看護協会無料職業案内「ナースバンク」では、長時間勤務しなくて済む個人宅で働きたいと登録しているナースに対する求人はたった1.7%。
「組織」ゆえのストレイスから離れ
お客様と自分の事だけ考えて個人宅で短時間で働く事ができる
そんな「ナーシングドゥーラ」という働き方なら、
自分の健康と家族の暮らしと看護を両立することができるひとつの働き方です。
そして、今まで寄り添いたくても寄り添えなかった方たちほ支えられる、まさに地域子育て支援の救世主です。
ぜひ、あなたも、ナーシングドゥーラ®として、地域の子育て支援に貢献してください。